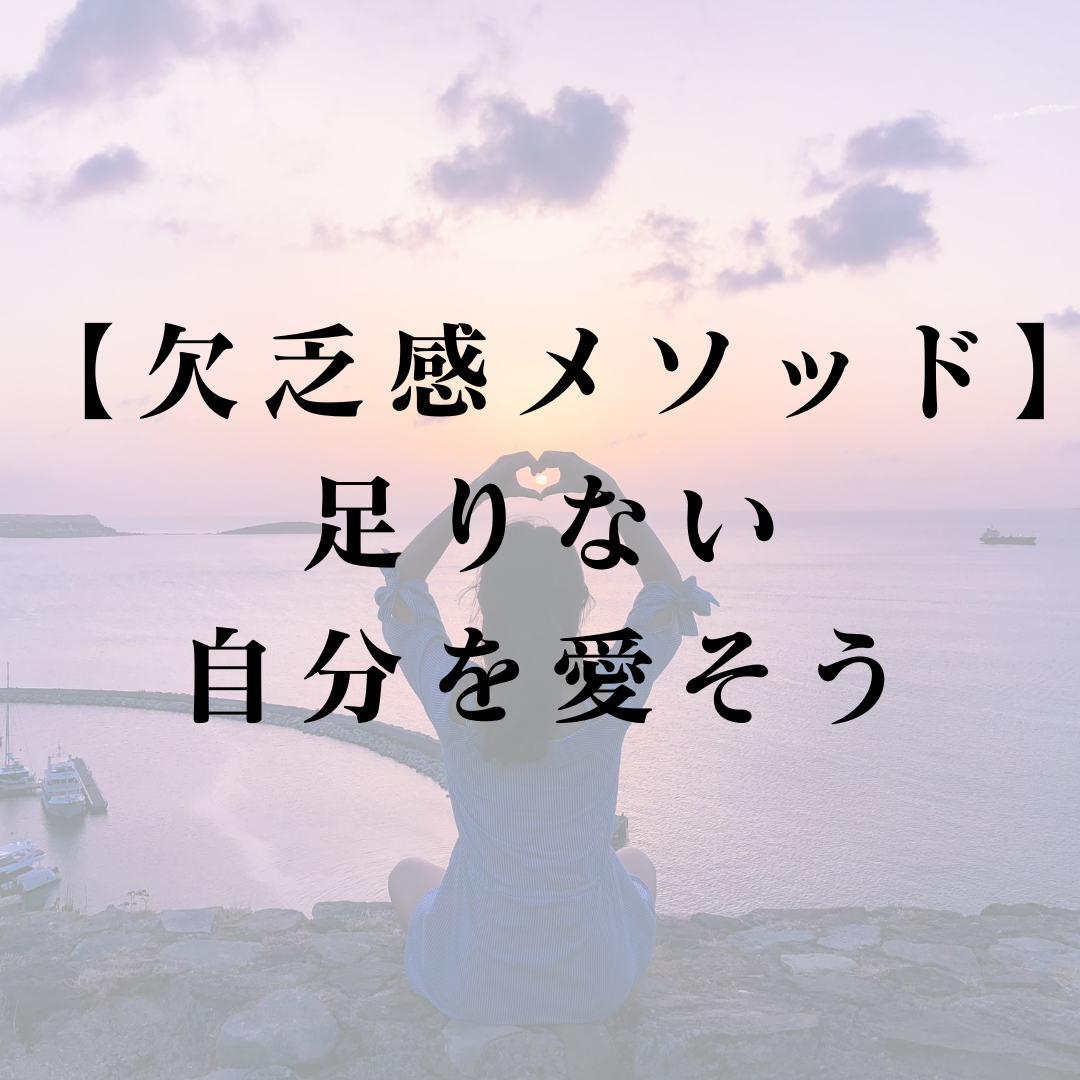
「どうすれば、この満たされない感覚から解放されるんだろう?」
そう思ったことはありませんか?
満たされない思い、不安、焦り、劣等感――それらを「満たそう」とするたびに、かえって苦しくなっていく。
前回の記事では、欠乏感よって起きている苦しみのメカニズムについて書かせていただきました。
今回は、この“欠乏感とのつきあい方”について考えてみます。
欠乏を「満たそう」とすると、かえって苦しくなる
私たちはつい、欠乏を「満たす」ことで幸せになれると思いがちです。
「もっと自信を持てれば」「認められれば」「何かを手に入れられれば」……そうすれば、この心の空白も埋まるだろうと。
でも実は、「満たそう」とするその姿勢自体が、さらなる苦しみを生むことがあります。
なぜなら、「欠乏があるのはよくないことだ」と決めつけると、“そうでない自分”を目指して、いつまでも「今の自分」を否定し続けてしまうからです。
それは、「あるべき自分」と「今の自分」とのズレを、永遠に埋めようとすること。けれど、そのズレこそが、苦しみの正体なのかもしれません。
欠乏感を受け入れることで、自由が生まれる
欠乏感とは「この現実はダメだ、嫌だ」という欠乏に対する抵抗心ですが、欠乏感そのものは勝手にはなくなりません。
しかし、それを「受け入れる」ことで、欠乏感に支配されずに生きることが可能になります。
これは、「自分の欠けた人生に絶望し諦める」ということではありません。
むしろ、「欠けたままの自分でも、生きていく」「愛していく」と決める能動的な選択なのです。
「受け入れる」とはどういうことか?
受け入れるというのは、まず欠乏感を感じていることを認めることから始まります。
「怖い」「寂しい」「足りていない」といったその感情にフタをせずに、ありのまま向き合うことが受け入れるための第一歩です。
そして、そのうえで自分に問います。
「では、自分はこの欠乏感とともに、どう生きていくのか?」
ここでふたつの選択肢が生まれます。
・欠乏を埋めることを目的にして生きる(=恐れから逃れるための人生)
・欠乏を抱えたまま、自分の価値をもって生きる(=選びとる人生)
受け入れるとは、後者を選ぶことです。
それは、たとえばこういう姿勢と言えるでしょう。
・「欠けた自分」を否定せずに引き受ける強さ。
・「満たされない不安」を抱えながらも、人を信じ、愛する勇気。
・他人や過去を責めるのではなく、「それでも私はこう生きる」と選ぶ覚悟。
確かに、欠乏と正面から対峙し、それを乗り越えていくというのはとても恐いと思います。
それでも、恐くても前に進んでいくんだという姿勢が、欠乏感を受け入れていくことに繋がるのです。
欠乏を受け入れる日常の実践例
①仕事での自信のなさに向き合うとき
日々の仕事で、自分のスキルや成果に不安を感じることはありませんか?
例えば、大きなプレゼンの前に「自分なんてうまくできるはずがない」と思ってしまう瞬間。
そのとき、欠乏感が「私は十分じゃない」「もっとできる自分にならなきゃ」と囁いているのです。
ここで重要なのは、「自分は今、欠けた部分がある」と認めることです。
そして、それを否定せずに受け入れる。
「完璧でない自分でも、このプレゼンを頑張ってやってみる」「精一杯やった結果失敗したり笑われたとしても、それが自分なのだからその未来を恐れない」「欠けた自分として生きよう」と選ぶことで、欠乏感を抱えたまま前進する覚悟を持つことができます。
例えば、プレゼン前に深呼吸をして、自分の不足を認め、少しの不安とともに「結果よりも過程を大切にしよう」「失敗しても自分を責めず、次に生かそう」と自分に言い聞かせる。
この一歩が、欠乏感に支配されない生き方の始まりです。
②人間関係の中で感じる孤独感に向き合うとき
友人やパートナーとの関係において、ふとした瞬間に孤独を感じることがあります。
「もっと愛されていたら」「もっと大切にされていたら」と思うこともあるでしょう。
この孤独感を解消しようと、相手に過剰に期待したり、自分を無理に合わせようとすることが、さらなる苦しみを生む原因になってしまうことも。
そのとき、欠乏感を受け入れる方法は、まず自分の心に正直になることです。
「今、私は愛されていないと感じている」と認め、その感情を無理に消そうとするのではなく、静かに感じる時間を持つ。
そして、相手に対して「愛されることを期待する気持ち」を認めつつも、「相手はコントロールできないのだから相手がどうするかよりも自分がどうしたいかに焦点を当てよう」と自分の行動に焦点を当てていくことが大切です。
例えば、相手がデートに誘ってくれないのなら、自分から誘う。
相手がどうしたら喜ぶかを考えて接していく。
それにより、他人に過度に依存せずに、心地よい関係を築くことができるのではないでしょうか。
③将来への不安と向き合うとき
未来に対して漠然とした不安を抱くことも、欠乏感の一つです。
「このままで本当に大丈夫だろうか」「自分はまだ十分な準備ができていない」といった不安が押し寄せることもあります。
この不安を受け入れるためには、「今、自分には不安がある」と認め、未来の結果に過度に執着しないことが重要です。
「どうなるか分からないけれど、今できることを精一杯やってみよう」「どんな未来になろうと、その人生を歩んでいこう」と自分を励ますことで、欠乏感を感じながらも進むことができます。
例えば、夜寝る前に自分の不安に向き合って、その不安を感じることを許し、次の日に向けて小さな一歩を踏み出すこと。
たとえ不安が残っていても、「それでも今を生きる」と決めることが、欠乏感を受け入れる強さに繋がります。
欠乏を受け入れるということ
最後に。
欠乏感を受け入れるというのは、ただ感情を処理することではありません。
「欠乏したままの自分」と一緒に生きていく覚悟を持つことです。
それはきっと、「今の自分」を見つめ直す勇気であり、「未来に何があっても、自分として生きていく」という選択です。
欠けたままでも、足りないままでも、愛されないとしても。
それでもなお、私は、私として生きていく。
そんなふうに決めたとき、欠乏感はもはや、あなたを縛るものではなくなっているはずです。
まとめ
欠乏感は、欠乏のある人生を選択していくことで癒されていきます。
欠乏に対する恐れをなくすことは難しい。
だからせめて欠乏感を抱えてもなお強く生きるという覚悟が出来ることが大切なのではないでしょうか。
次回の記事では、実際にワークに取り組んでいただこうと思います。
次の記事はこちら!